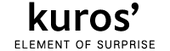染めの現場を歩く 丸久商店の注染工場にて。
午後13時、染めが行われている染工場に到着。
案内してくれたのは、丸久商店5代目の斉藤美紗子さん。連れていってくださったのは、総勢10名ほどの職人たちが黙々と働く注染の工場。足元には、おがくずが敷き詰められ、あちこちに束ねられた一反の布が無造作に置かれている。
足元に気を配りながら進むと、染料の香りと、不規則に鳴り響く機械音に包まれた。

足元にはおがくずが。
それぞれの職人たちは自分の持ち場で、染料で汚れたエプロンとゴム手袋姿で手を動かしている。その姿には誠実に布と向き合う姿勢が滲んでいた。
kuros’のために染め上げていただいた布を発見。
「職人が、染料の入った薬缶(やかん)と呼ばれるじょうろのような道具を両手に、傾けながら少しずつ慎重に布へと色を流し込んでいく。濃淡の加減は、その時々の手の動きや感覚で決まるもので、熟練の技と感性によってできるもの。
その染色の様子から「注染」と呼ばれるようになったそう。
繊細で静かな手の動きに、思わず目を奪われた。
注染の工程は、まさに感覚がものを言う世界。
真っ白な生地を何層にも折り畳むところから始まり、染料を丁寧に染み込ませる工程、水を流す川のような機械で糊を洗い流す工程、そして染め上がった布を高い場所から吊るして自然に乾かす工程まで。どの作業も、ひとつとして気の抜けない繊細な仕事だった。

染色しない場所に糊をつけて保護する工程。端で折り返しながら何層にも折り畳んでいく。

濃淡のグラデーションを左右のやかんで調節しながら染色している。

布に付着している糊を水の中で揺らし、洗い流す機械

糊を洗い流した布を高い場所から吊るして乾かしている。
ひととおりの工程を見せてもらい、職人の動きを追っているうちに、まだ形になっていない布たちがとても魅力的に見えてくる。完成を想像するだけでワクワクして、既にもう欲しくなっていた。
じっくりと工場を見学させてもらったあと、改めて5代目・斉藤美紗子さんに、たっぷりとお話を伺った。